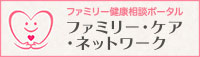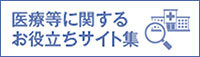健康保険に加入する人
本人:被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人事業所は法律によって、事業主や従業員の意思に関係なく健康保険に加入しなければならないことになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
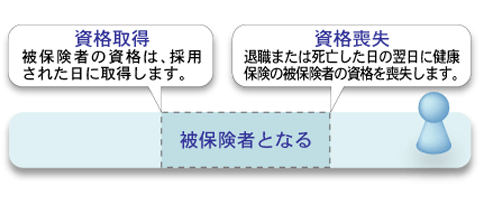
家族:被扶養者
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
|
【注意】
|
(1)生計維持関係
被扶養者としての認定を受けることができる人は、主として被保険者の収入により生活している家族です。
したがって、被保険者の収入が下表の世帯人数に応じた生計費(年額)に達していない場合は、被保険者の収入により生活できていないと判断します。
なお、被扶養者に収入のある者の取扱いは、以下(2)収入限度額のとおりとします。
| 標準生計費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 世帯人数(※) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
| 生計費(年額) | 130万円 | 200万円 | 230万円 | 270万円 | 300万円 |
- ※被保険者および被扶養者の人数(左記以外の者は含めない)。また複数に別居している被扶養者がいる場合は別居世帯ごとの被扶養者数。
- ・標準生計費は人事院の発表に基づき、毎年見直します。
- ・生計費(年額)は同世帯の被保険者および被扶養者の収入の合計額です。
- ・世帯人数が6人以上の場合は、30万円/人を上乗せした金額とします。
(2-1)収入限度額
被扶養者の範囲にある者の収入が年間130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であること。
- ・年額について
被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間見込収入額が下表の(年額)を超過していないか判断します。 - ・月額について
雇用契約等により月額収入が概ね固定されている場合は、下表の(月額)を超過していないか判断します。
(パート・アルバイトによる給与収入等) - ・日額について
失業給付や出産手当金、傷病手当金の受給により、日額が下表の(日額)を超過していないか判断します。
| 60歳未満の収入限度額 | 19歳以上23歳未満 (被保険者の配偶者を除く) |
60歳以上または 障害年金受給者の収入限度額 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| (年額) | 130万円未満 | (年額) | 150万円未満 | (年額) | 180万円未満 |
| (月額) | 108,333円以下 | (月額) | 124,999円以下 | (月額) | 149,999円以下 |
| (日額) | 3,611円以下 | (日額) | 4,166円以下 | (日額) | 4,999円以下 |
(2-2)収入の範囲
所得税の課税・非課税を問わず生活に充当できる収入が対象となります。
-
- ○給与収入(※1)
- ○事業収入(※3)
- ○一時収入(※4)
-
- ○年金収入(※2)
- ○労働保険、社会保険の給付金
- ○その他、生活費に充当できる収入
-
- ○恩給(※2)
- ○利子、配当収入
- (※1) 賞与、残業手当、交通費を含む
- (※2) 年金(恩給)収入は金額の通知時点で年額が確定していることから、1年分の収入があったものとして取扱います。
- (※3) 事業収入は総収入額から、直接的必要経費(◆)を差し引きした額とする。
◆詳細は『関西電力健康保険組合が認める「直接的必要経費」一覧表』参照 - (※4) 各種私保険の満期金や解約返戻金等、1回限りで受取るような一時的な収入については含みません。
収入に含めない
(継続性がないものに限る)不動産・株式等の売却(譲渡)による収入 相続による預貯金 保険等の満期金・解約返戻金 一時金として受け取る退職金 (令和6年1月以降)
(3)被扶養者の範囲(3親等以内の親族)
| 被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
|---|---|
|
|
もっと詳しく
- 3親等以内の親族表閉じる
-
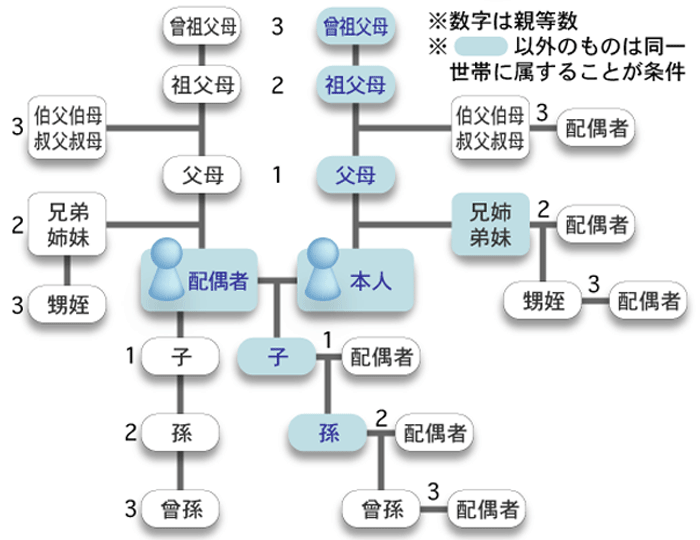
- パート・アルバイトによる収入がある場合閉じる
-
年間収入が130万円未満(同上)であり、月額108,333円以下であること。
なお、所定労働時間および所定労働日数が当該事業所の通常就労者の3/4以上であると判断される場合は、本来被保険者となることから、扶養者として認定できません。- ※勤務先に正社員がいない場合は、通常就労者の平均的な所定労働時間8時間/日、および所定労働日数22日/月を基準に、3/4の条件に該当するかどうか判断します。業種によっては、所定労働時間・日数が大きく異なる場合もあるため、必要に応じて勤務先で証明された「勤務形態証明書」を提出していただき判断します。
- ※収入が限度額以内であっても、被扶養者の勤務先で健康保険の資格がある場合は、扶養者として認定できません。
(勤務先で資格を取得された場合は、速やかに異動減の手続きを行ってください。)
- 別居の場合閉じる
-
収入が130万円未満(同上)であり、かつ、被保険者からの仕送りが被扶養者の収入を上回っており、かつ、被扶養者の収入と仕送りの合計額が標準生計費を上回っていること。
また、毎月、一定額の仕送りを行うことができ、書面で確認できること。
- 雇用保険法による失業給付等や、健康保険法による傷病手当金・出産手当金を受給する場合閉じる
-
原則として扶養者と認定できません。ただし、失業給付や傷病手当金、出産手当金の額が日額で3,611円(4,999円)以下の場合は、この限りではありません。
- 事業(営業等・農業)収入がある場合閉じる
-
名義のいかんにかかわらず、実際に誰が従事しているのか、その実態により判断します。
被扶養者から被保険者への給与や工賃の支払いは経費として認定しない。
- 共同で生活を支えている方(共同扶養者)が存在する場合の取扱い閉じる
-
被扶養者を認定するにあたって、共同で生活を支えている方※(共同扶養者)が存在する場合、申請者(被保険者)と共同で生活を支えている方(共同扶養者)と双方の収入を確認しますので、「共同扶養における収入額確認表」と必要書類を添付してください。
- ※該当する方
・被扶養者になっていない配偶者
・届出しようとしている被扶養者と同一世帯である他健保等の被保険者(父母、兄弟、姉妹等)
なお、同収入限度額内であっても、被保険者の収入・生計維持関係等により認定できない場合があります。
- ※該当する方
- 父母の両方、またはどちらか一方を扶養しようとする場合閉じる
-
父母は互いに共同扶養の関係になるので、被保険者の年収と比較を行い、父母どちらかの年収が被保険者の年収を上回る場合は、他方の父母を被扶養者として認定できません。
また、同一世帯に他の家族(兄弟など)がある場合は、収入の多い人の被扶養者となります。
被扶養者認定の取扱い
- 被扶養者の範囲にあり、生計維持関係を認定した者に被扶養者資格を付与します。
- 原則として健康保険組合受付日にて認定します。
ただし、以下の場合は事象発生日まで遡って認定します。
書類到着が遅れそうな場合は、「健康保険被扶養者異動届」の左下「遡及理由(届出遅延理由)申立書」に、その理由を記入し、署名・捺印があれば、健保組合への到着(受付日)が、事象発生日の翌日から起算して30日以内であれば、事象発生日に遡って認定いたします。(申請内容に不備があった場合は、不備解消後の再受付月日が事象発生日の翌日から起算して30日以内とします。)
【注意】申立書の記載がある場合でも健康保険組合への到着が大きく遅れた場合は、健康保険組合受付日にて認定します。
| 事象発生日について | 健康保険組合受付前に被保険者(被扶養者)資格を喪失している場合に限り、下記に該当する日付を「事象発生日」として認定します。(健保受付日が事象発生日の翌日から起算して30日以内に限る) (1)同居日 (2)資格喪失日 (3)退職日の翌日 (4)自営業廃止日の翌日 (5)養子縁組日 (6)仕送り日 (7)その他、被保険者が主たる生計維持者であると認めることができる日 |
|---|
- ・生計維持関係は添付書類等により判断します。
もっと詳しく
- 国外居住者について開く
被扶養者削除の取扱い
下記の事象が発生した場合、扶養削除となりますので速やかに届け出てください。( )内は削除日
-
- ○就職(資格取得日)
- ○離婚(離婚日、または別居の日)
- ○結婚(結婚日)
- ○被保険者の収入の減少等による
主たる生計維持者の変更(事実発生日) - ○75歳到達(誕生日)
- ※後期高齢者医療制度の被保険者となる
- ○雇用保険受給(日額3,611円を上回る)(受給開始)
- ○死亡(死亡日の翌日)
-
- ○収入限度額超過
- ・年金(恩給)の場合は、通知書発行月の翌月1日
- ・確定申告書(自営業者等)の場合は、収入が超過したことが確定した日。ただし、収入の確定が「3月1日」以後となる場合は、「3月1日」とする。
- ・明確な収入超過日が不明である場合は、事実確認のうえ、事象発生日を判断する。
- ○収入限度額超過
- ●なお、資格喪失日以降に医療費等の保険給付がある場合は、後日精算させていただきます。
75歳以上の被扶養者
75歳(寝たきりの人は65歳)を過ぎると、被扶養者も被保険者と同じように、医療を受ける場合は健康保険から後期高齢者(長寿)医療制度に切りかえられます。よって健康保険組合の被扶養者としての資格は失われますので、被扶養者の異動手続きが必要となります。