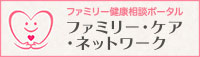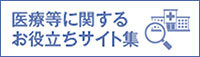高齢受給者証、限度額適用認定証など
- 解説
- 手続き
高齢受給者証
70~74歳の被保険者および被扶養者は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されます。一部負担割合は所得に応じて2割または3割となっているため、一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます。なお、負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。
- ※2024年12月2日以降、「高齢受給者証」は、原則、「資格確認書」を持つ方に対し交付します。
特定疾病療養受療証
血友病等特定疾病の治療を受ける際に、「資格確認書」とあわせて病院の窓口に提出することで、1ヵ月の医療費自己負担額が軽減されます。
※この証の交付を受けるには、当健康保険組合へのお手続きが必要です。
- ※2024年12月2日以降、「特定疾病療養受療証」は、原則、「資格確認書」を持つ方に対し交付します。
限度額適用認定証
70歳未満の者が1ヵ月に同一医療機関で入院等の療養を受けた際に、「資格確認書」とあわせて病院の窓口に提出することで、所得区分に応じて窓口負担額の支払いを高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。
なお、その額を超える部分については、健保組合から医療機関等に直接支払われます。
- ※「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
「マイナ保険証」の利用が不可である場合、事前に健康保険組合への申請を行ってください。 - ※2024年12月2日以降、「限度額適用認定証」は、原則、「資格確認書」を持つ方に対して交付します。
限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証
低所得者(市町村民税非課税者)と認められた場合、「資格確認書」とあわせて病院の窓口に提出することで、窓口負担額の支払いを高額医療費の自己負担限度額までにとどめることができるとともに、入院時食事療養費の標準負担額の減額が受けられます。
- ※2024年12月2日以降、「特定疾病療養受療証」は、原則、「資格確認書」を持つ方に対し交付します。
| 書類提出先 | |
|---|---|
| 在籍者(関西電力㈱、関西電力送配電㈱) | 関電オフィスワーク 人事サービスチーム(※1) |
| 在籍者(上記以外の会社) | お勤め先の健康保険担当箇所(※1) |
| 退職者(任意継続被保険者) | 関西電力健康保険組合 |
※1:「特定疾病療養受療証」、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請のみ、健康保険組合への直接送付が可能です。
高齢受給者証や資格確認書などを失くしたときや破損等したときの手続き
高齢受給者証、資格確認書を失くしたり、破損等してしまったら、ただちに再交付の手続きを行ってください。
- ※高齢受給者証や資格確認書などを失くした場合は悪用されることがありますので、すみやかに最寄の警察署へ届け出てください。
- ※盗難や紛失の場合であっても、健康保険組合で資格を無効とすることができません。よって、不正使用により生じた損額等は補償できませんので、お取り扱いにはご注意願います。
| 必要書類 |
|
|---|---|
|
|
(添付書類)
|
|
| 備考 |
|
- ※2024年12月2日以降、「高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」は、原則、「資格確認書」を持つ方に対して交付します。
被保険者や被扶養者の氏名に変更のあったときの手続き
改姓・改名した日から5日以内に提出してください。
| 必要書類 |
|
||
|---|---|---|---|
|
|||
| 備考 |
事実確認のため上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
|
||
被扶養者の住所に変更のあったときの手続き
被扶養者の住所に変更があったときは、速やかに提出してください。
(被保険者と同時に転居する場合、住所変更届は、事業主を通じて提出されるため、不要です)
| 必要書類 |
|
|---|
被保険者の資格を失ったとき
資格を失った日から5日以内に返納してください
| 必要書類 | ・資格確認書(交付されている方のみ) ・高齢受給者証など(交付されている方のみ)・限度額適用認定証 |
|---|